以下、本文になります
トピックス
【新島塾】「読書から始まる知の探究」小山先生セッション_第1回活動
2025年4月17日 更新
2025年3月22日(土)・4月12日(土)、小山 隆 教授(社会学部)による「読書から始まる知の探究」 第1・2回学習が行われました。
本セッションは社会学部社会福祉学科の小山隆教授のご指導のもとで、約半年間に渡り、塾生自身が主体的にフィールドやテーマを設定し、探究活動を行う形式で実施されます。
また、このセッションには5期生(一部)と6期生が参加します。
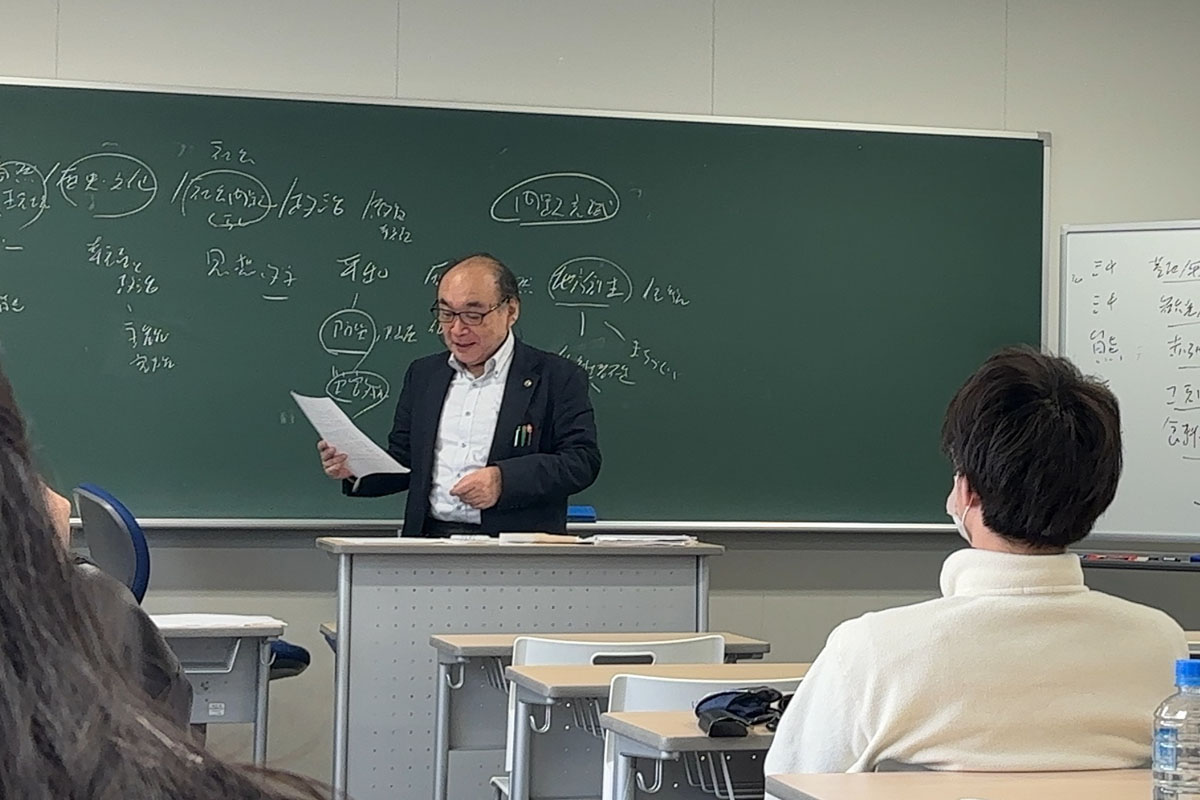
第1回目セッションの1講時では、まず初めに小山先生から本セッションの目的や意義、活動にあたって気をつけるべき点などに関してお話がありました。特に、本セッションは学生が主体で行うため、フィールドワーク先のアポイントメントの取り方や合意形成の方法などをお話しいただきました。その後、塾生による個人の事前課題の発表がありました。事前課題の内容は次の通りです。
1.自分が関心のあるテーマを挙げる
2.フィールドワークにふさわしいと考える場所を挙げる
3.テーマ設定
(上記2.で取りあげることができそうなものを2~3案)
各塾生が関心のあるテーマをそれぞれの視点から発表しており、 十人十色の発表をみることができました。全体を見てみると、フィールドワーク先として東北をあげている人が多く、他には東京都や九州の県をあげている人もいました。フィールドワーク先からその場所にある課題を考えている人や逆に課題から考えて場所を決めている人もいました。それぞれが熱意のあるプレゼンテーションをしており、他の塾生から質問が出る場面や課題の捉え方に対して議論が起こる場面など今後のセッションが楽しみになりました。
1.自分が関心のあるテーマを挙げる
2.フィールドワークにふさわしいと考える場所を挙げる
3.テーマ設定
(上記2.で取りあげることができそうなものを2~3案)
各塾生が関心のあるテーマをそれぞれの視点から発表しており、 十人十色の発表をみることができました。全体を見てみると、フィールドワーク先として東北をあげている人が多く、他には東京都や九州の県をあげている人もいました。フィールドワーク先からその場所にある課題を考えている人や逆に課題から考えて場所を決めている人もいました。それぞれが熱意のあるプレゼンテーションをしており、他の塾生から質問が出る場面や課題の捉え方に対して議論が起こる場面など今後のセッションが楽しみになりました。
2講時では、先ほどの発表を引き続き行なったのちに、塾生それぞれの発表をまとめて相違点を整理しました。また、それぞれの発表から要素を取り出して整理しました。分野としては産業や文化、思想、社会問題、政治、平和、IT、防災などが挙げられました。
次回に向けて、今回整理した要素を個人で構造化してさらに深めるという課題が出ているので、塾生は各自その課題に取り組み、次回以降に今夏に予定しているフィールドワークに向けて深みのある議論を目指します。
今回のトピックスは、以下の塾生が作成しました。
新島塾第6期塾生 梅田さん(文化情報学部)
新島塾第6期塾生 田中さん(政策学部)
新島塾第6期塾生 中村さん(政策学部)
第2回セッション1講時では、第1回セッションにて課された事前課題を全体の前で発表しました。
事前課題は
1. 第1回セッションにて整理を行なった各々の関心のあるテーマ・地域に関する情報から要素を抽出し構造化を行なう。
2. 自身の関心のあるテーマと結びつける
3. 課題を取り上げる意義について書く
という3つの要素からなるものでした。今回の発表内容は、前回のセッションにて整理した情報を基に構造化を行なったものであったため、前回と比較して目標が明瞭かつ簡潔なものになっており、塾生間の調整が取りやすくなったように思われました。
発表の内容については、構造化というプロセスを通じて前回セッションで定めた設定に磨きをかけていた人や、前回のセッションを踏まえて新しい・より広げた課題設定を行なう人など様々であり、各々の興味関心についての理解を更に深めることが出来ました。
1. 第1回セッションにて整理を行なった各々の関心のあるテーマ・地域に関する情報から要素を抽出し構造化を行なう。
2. 自身の関心のあるテーマと結びつける
3. 課題を取り上げる意義について書く
という3つの要素からなるものでした。今回の発表内容は、前回のセッションにて整理した情報を基に構造化を行なったものであったため、前回と比較して目標が明瞭かつ簡潔なものになっており、塾生間の調整が取りやすくなったように思われました。
発表の内容については、構造化というプロセスを通じて前回セッションで定めた設定に磨きをかけていた人や、前回のセッションを踏まえて新しい・より広げた課題設定を行なう人など様々であり、各々の興味関心についての理解を更に深めることが出来ました。
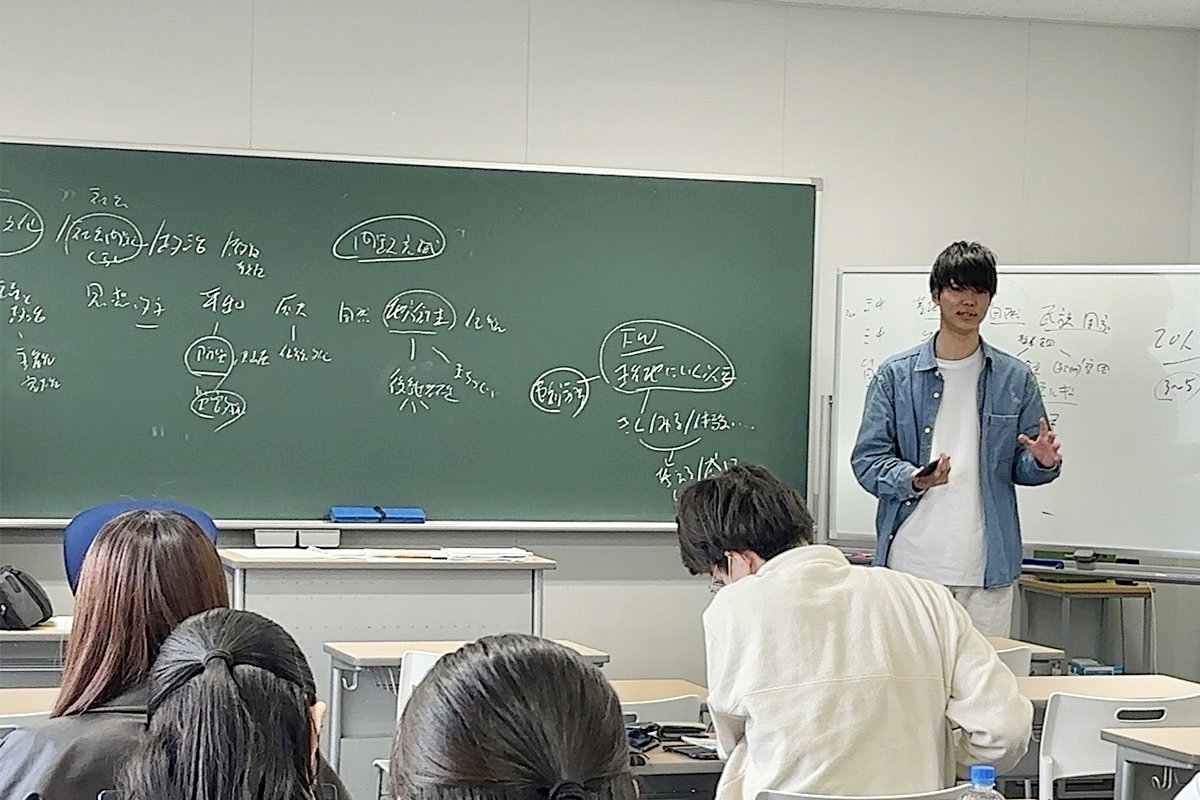
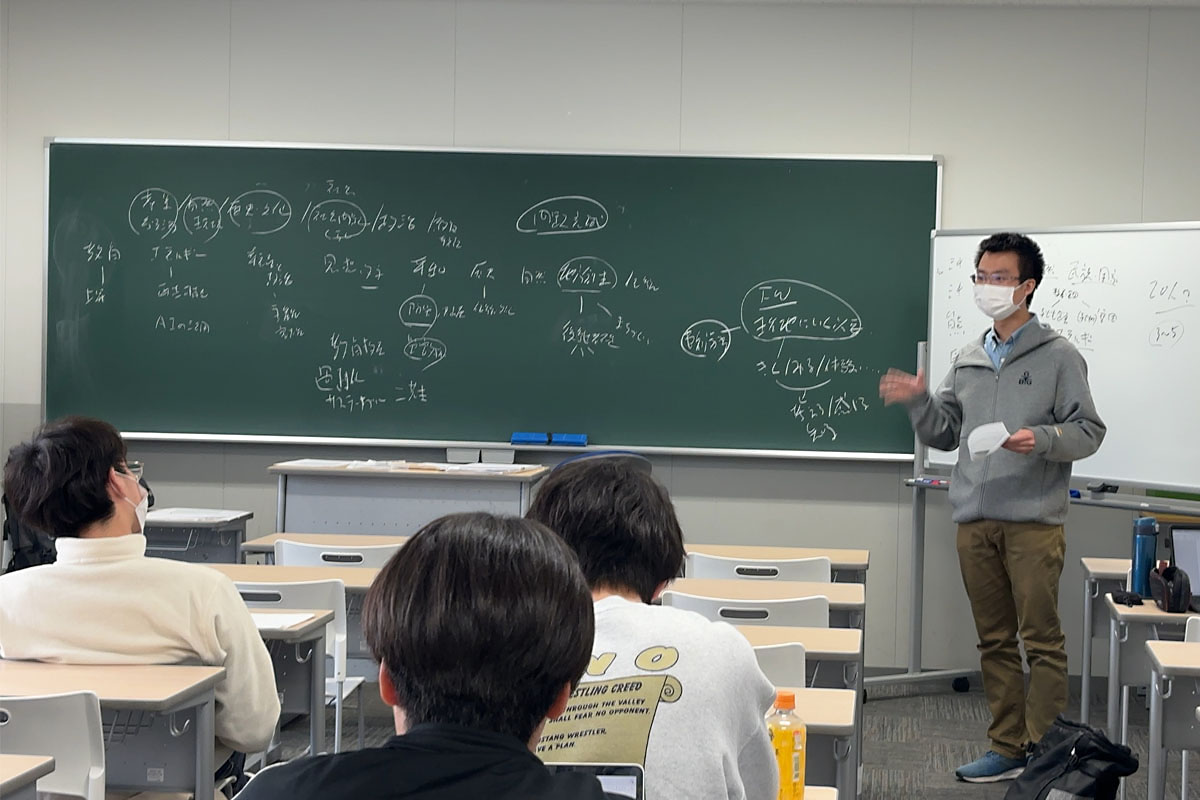
2講時には、「産業」「社会問題・暮らし」「自然・環境」「文化・歴史」「政策」というテーマを軸として、個人の関心に合わせて5つの班に分かれました。そして、そのテーマでどのようなことを学びたいか、どこへ足を運びたいかについて話し合いました。
以下に、各班の発表内容を紹介します。
産業班は、行先として、筑波研究学園都市を挙げました。筑波研究学園都市は、日本最大規模の科学技術集積地であり、現代産業の中核を担う研究機関が多く集まる場所です。加えて、震災や水戸学などの観点からも、筑波は横断的に学ぶことができる地域であると考えました。
社会問題・暮らし班は、防災と地方創生について検討し、それらの根幹にある概念として幸福を考えました。幸福度の観点から福井県と岩手県を行先の候補とし、行政と合わせて幸福を考えるという案が出されました。
自然・環境班は、自然と人間の共生に関する学びを提案しました。フィールドワークの特徴を考慮し、土地との結びつきが強いこのテーマこそ、フィールドワークとして学ぶ意義があると考えました。具体例として白神山地が挙げられました。
文化・歴史班は、地域性を反映した伝統文化を学びたいと話しました。どこの地域もそれぞれの文化をもっており、他のテーマと結びつけて考えることもできそうだと考えました。
以下に、各班の発表内容を紹介します。
産業班は、行先として、筑波研究学園都市を挙げました。筑波研究学園都市は、日本最大規模の科学技術集積地であり、現代産業の中核を担う研究機関が多く集まる場所です。加えて、震災や水戸学などの観点からも、筑波は横断的に学ぶことができる地域であると考えました。
社会問題・暮らし班は、防災と地方創生について検討し、それらの根幹にある概念として幸福を考えました。幸福度の観点から福井県と岩手県を行先の候補とし、行政と合わせて幸福を考えるという案が出されました。
自然・環境班は、自然と人間の共生に関する学びを提案しました。フィールドワークの特徴を考慮し、土地との結びつきが強いこのテーマこそ、フィールドワークとして学ぶ意義があると考えました。具体例として白神山地が挙げられました。
文化・歴史班は、地域性を反映した伝統文化を学びたいと話しました。どこの地域もそれぞれの文化をもっており、他のテーマと結びつけて考えることもできそうだと考えました。
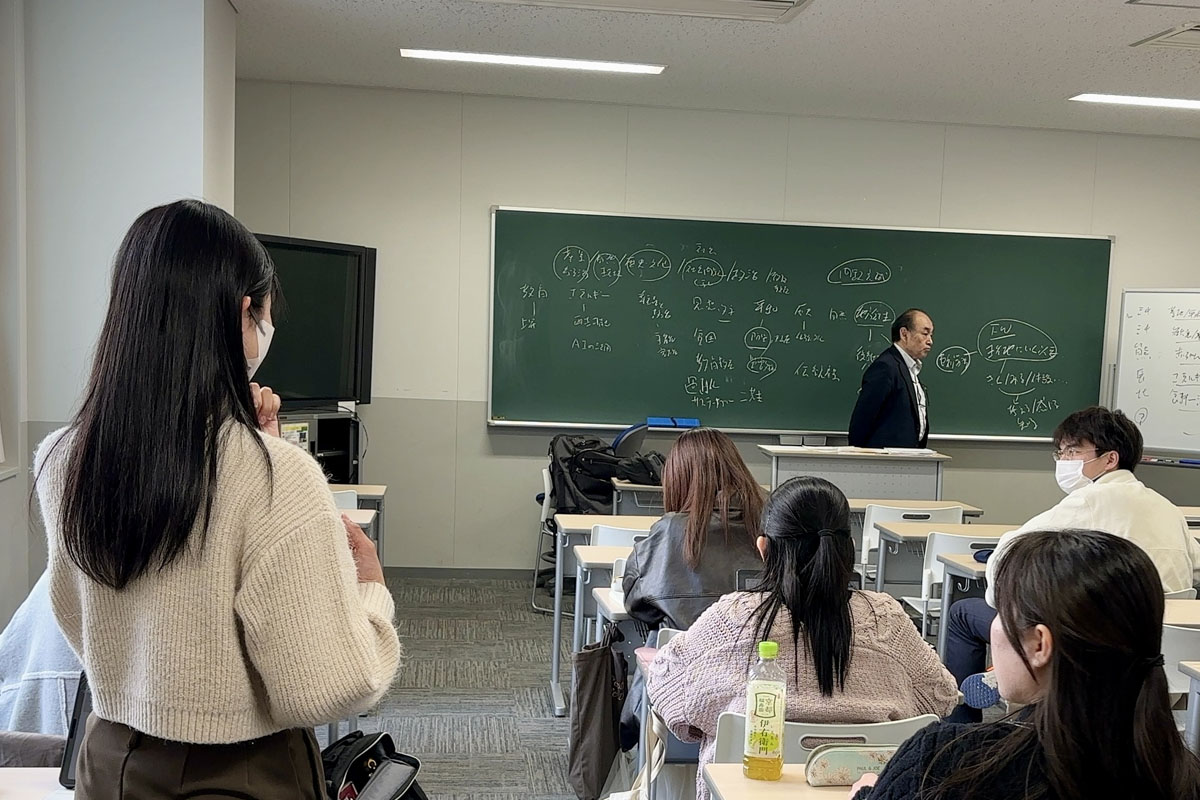


政策班は、政策の作られる過程に着目しました。政策デザインと実状の差異を念頭に、政策がどう機能しているか(していないか)や、民意と効率の間に生じるジレンマについて体感したいと話しました。
次回のセッションに向けて、事前課題では「地域×テーマ」の組み合わせについて考えます。次回以降、フィールドワークの行先やテーマを固めていく予定です。塾生の関心に関連した学びができるよう、話し合いを重ねていきます。
次回のセッションに向けて、事前課題では「地域×テーマ」の組み合わせについて考えます。次回以降、フィールドワークの行先やテーマを固めていく予定です。塾生の関心に関連した学びができるよう、話し合いを重ねていきます。
(事務局・高等研究教育院事務室)
今回のトピックスは、以下の塾生が作成しました。
新島塾第6期塾生 池田さん(心理学部)
新島塾第6期塾生 川本さん(文学部)
| 関連情報 |
VISION2025 新島塾特設サイト 新島塾の詳細はこちらからご覧ください。 |
|---|
| お問い合わせ |
高等研究教育院事務室 TEL:075-251-3259
|
|---|