トピックス
【新島塾】「読書から始まる知の探究」小山先生 ~福島FW~ ■福祉班■
福祉班では、震災後の福島における心のケアや福祉支援の現状を学ぶことを目的に、ふくしまこころのケアセンターおよび福島県立医科大学を訪問しました。

福祉班
1日目
1日目
ふくしまこころのケアセンターを訪問し、実際の支援活動の現場を見学しました。センターでは、震災後の心のケアとして実施されているカウンセリングやグループ活動の様子を紹介していただきました。
職員の方々からは、相談者のニーズに応じた個別対応や、地域との協力体制の構築の重要性について具体的な事例を交えて説明していただきました。また、震災当時から現在までの支援の変遷や、今後の課題についてもお話しいただきました。
特に、長期的な心のケアの必要性や、若年層や高齢者への支援方法の多様化が求められている点が印象的でした。見学を通して、支援現場では日々の相談や活動が細やかに記録・評価されており、専門職の責任感と丁寧な対応が支援の質を支えていることを実感しました。


2日目
2日目
福島県立医科大学において、震災後の福島における心理的支援や福祉活動の概要について佐藤先生と竹林先生にインタビューをさせていただきました。インタビューでは、震災直後の避難生活に伴うストレスやトラウマ、また地域ごとの支援体制の違いについて詳しく説明していただきました。特に、震災によって家族やコミュニティを失った方々が抱える心理的影響は長期にわたり、支援の継続性が重要であることを学びました。また、医療機関だけでなく、地域住民やボランティアとの連携が不可欠であることも強調されていました。
さらに震災後の福島において特に子どもや高齢者が抱える心理的課題が深刻であると教えてくださいました。例えば、子どもたちは学校生活や友人関係において震災の影響を受けやすく、心のケアが遅れると学習や社会性の発達にも影響が出る可能性があると説明くださいました。高齢者についても、避難生活のストレスや孤立感が健康面に悪影響を及ぼす場合があり、年齢や生活状況に応じた支援の多様化が必要であることを理解することができました。
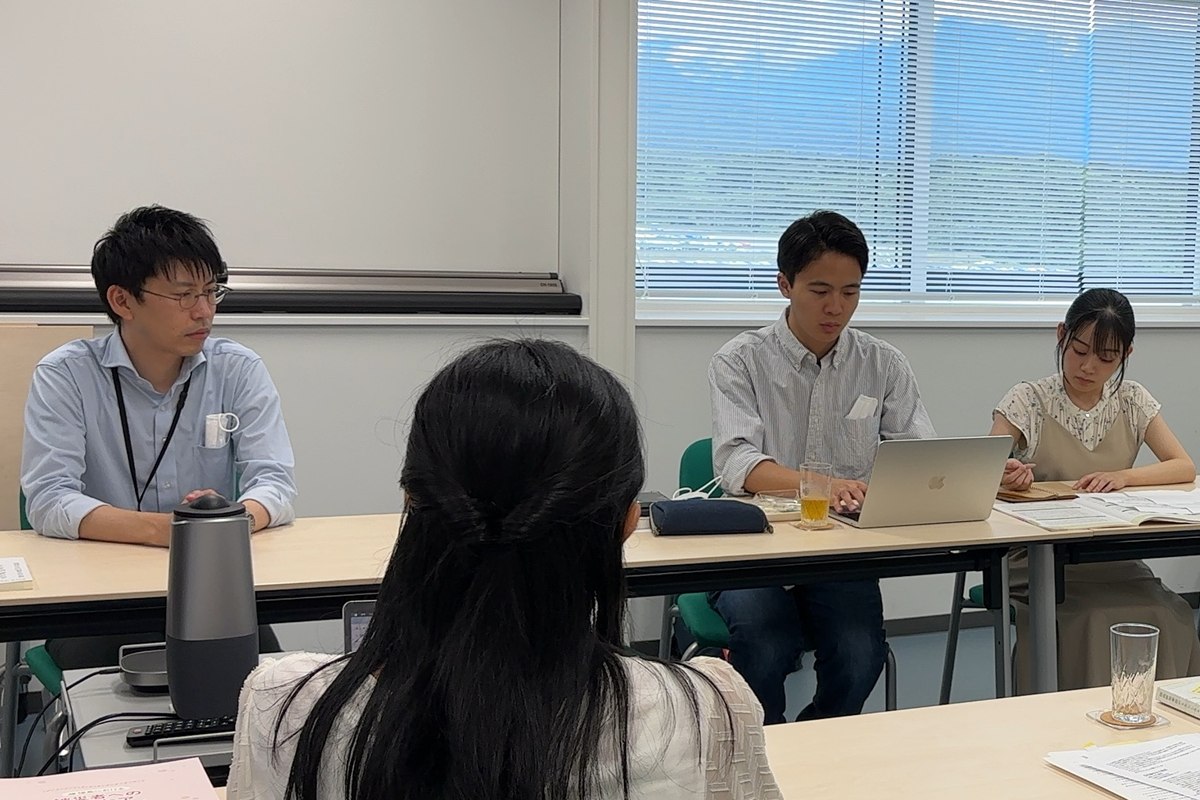
今回のフィールドワークを通して、震災による心の被害は目に見えにくい部分も多く、継続的かつ地域に根ざした支援が必要であることを学びました。また、福祉や心理支援は単独の活動では十分でなく、多職種連携や地域コミュニティとの協力が不可欠であることも理解しました。福祉班は、今後福祉や教育の分野で活動する際に、支援を受ける側の立場や地域特性を考慮した取り組みが重要であることを意識していく必要があると感じました。さらに、現場で実際に活動されている職員の方々の熱意や、相談者一人ひとりに寄り添う姿勢に触れ、福祉の現場がいかに人間味と実践力を求められるかを強く印象づけられました。
全体を通して、単に震災支援の知識を得るだけでなく、社会福祉や心理支援の実践において何を優先すべきか、どのような姿勢で取り組むべきかを考える契機となりました。
(事務局・高等研究教育院事務室)
今回のトピックスは、以下の塾生が作成しました。
新島塾第6期塾生 田中さん(政策学部)
| 関連情報 |
VISION2025 新島塾特設サイト 新島塾の詳細はこちらからご覧ください。 |
|---|
| お問い合わせ |
高等研究教育院事務室 TEL:075-251-3259
|
|---|